
福井県、住宅内避難見直しの報告書「教訓無視」 念願の防災に向けた悩みを抱える【福井県】
2025-03-29
著者: 海斗
原発事故時の住宅内避難について、原子力規制委員会の調査チームが28日、報告書を取りまとめた。被害時に住民へ避難指示を出したり、情報を扱う自治体に意見を求めて報告したという。特に福井県は「国の責任」にも触れ、原発7基が稼働する福井県の防災体制の甘さが指摘された。
住宅内避難の指針見直しについては、昨年の福島での半島地震後、東北電力女川原発(宮城県)の地元自治体から具体的な解除条件を示すよう求められたこともあった。また、避難の被害地域では、家屋の倒壊や物資の不足などの住宅内避難時の課題が相次いでいた。
原子力規制協議において、報告書案に対し、全国43自治体から251件の意見があった。石川県は「自然災害下の住宅内避難」の調査がされていないと指摘。一方、規制庁としては、自然災害が重大になった場合にどのような問題があるかは地域で違いもあり、現時点では明確ではないため、調査が難しいとされる。
北陸電力はある同県の自治体について、住宅内避難から避難へ切り替えを「総合的に判断することが必要」と記述した報告書に対して、「たとえば電気がストップしている時点で3日間の住宅内避難は困難ではないか」と意見した。
夏場に「停電で窓を閉め切った中では難しい」「オール電化住宅が増加する中、食品の調理器具や冷暖房器具の確保まで難しい」と具体的な状況に言及し、課題を指摘。被災した住民が避難所へ集まり、収容人数を超える恐れにも言及した。
福井県は、住宅内避難の持続期間を延長するための具体的な対策を模索している。また、国が責任を持ち、事象で放出された放射性物質を含む「プルーム」到達のシミュレーションを示したり、住宅内避難の生活を伝えるパンフレットなどを作成してほしいとの要望もされている。
調査チームの討論に参加した敦賀市の松村仁明・危機管理政策課長も、「住宅内避難の解消に向けた物資の確保や配給に関する国の方針や体制整備が必要」と話している。これにより、避難者サイドの住宅内避難の理解へ、対策運営が求められている。
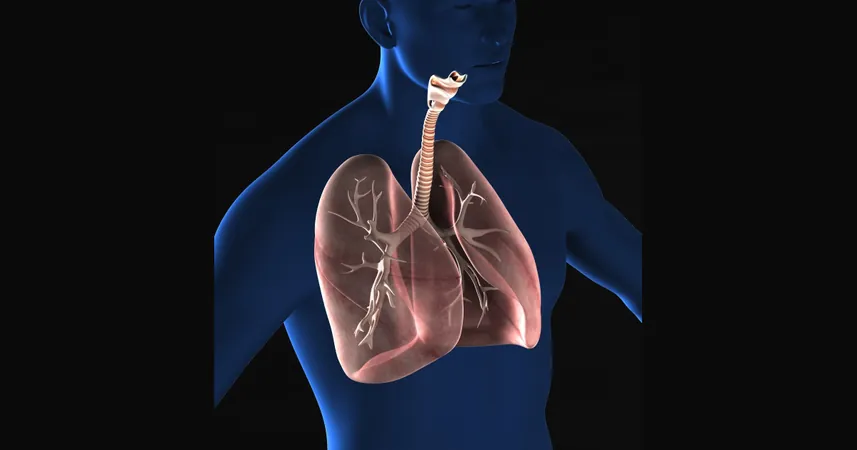


 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)