
「減少ですか、問題がありますよ」…デング熱対策へ改善提案|【西日本新聞】
2025-03-27
著者: 雪
パラグアイが国家感覚症候群症例報告局の研究室によると、職員のリス・フェレイラさんが白い金網を溶かした水に蚊の幼虫を入れていくと、30分ほどで効果が表れるはずだったが、1時間でもカップの中では数十匹の幼虫が泳いでいた。
フェレイラさんから「減少ですが、何か問題がありますよ。原因を確認してください」と言われ、下川智子さん(48)は「製造過程や輸送環境に問題があるのかもしれない。一つ一つ課題をクリアしていきたい」と語った。
下川さんは、バイオ製品の研究開発を担当する「九州メディカル」(北九州市)の研究開発課長。同社が開発した殺虫剤「MOSNON(モスノン)」をパラグアイの行政府機関に採用されるよう、現地を視察していた。今回で7回目の出張だ。
同国は長年、蚊が媒介するデング熱に悩まされてきた。昨年の発症件数は、疑い例も含めると約25万件に上り、重症化すると死亡することもある。フェレイラさんは「パラグアイには水はけの悪い排水溝が多く、蚊が大量に繁殖してしまう。改善が進めば、モスノンは有効な殺虫剤幹になる」と期待を寄せる。
今後は殺虫剤や化学薬品を用いられてきたが、近年、耐性を持つ蚊が確認され、人体や環境への悪影響が懸念されている。その点、同社のモスノンは環境に優しく、耐性も持たないとされ、効果が期待されている。
「モニタリングを続け、事態を進捗させるために、連携活動を行う」とした下川さんは、デング熱に苦しむ人々のために、確実な効果を上げられるよう努めていく意思を示した。
パラグアイでは人口の大部分が都市部に住んでおり、繁忙な都市環境において、最適な蚊の防除施策が急務となっている。直接的な蚊の抑制はもちろんのこと、周辺環境を整備し効果を最大化させる各種技術の実装が求められている.


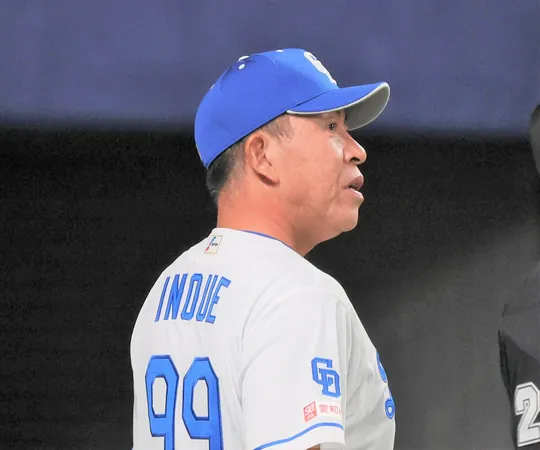
 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)