
気候変動とその影響を問う
2025-04-05
著者: 結衣
はじめに:なぜ気候モデルを問い直すのか?
地球温暖化対策の多くは、「今後の地球がどれほど気温上昇するか」という指標に依存している。その根拠となるのが、IPCCなどが採用する「気候モデル(GCM=General Circulation Model)」である。しかし、これらのモデルは万全ではなく、構造的な限界と仮定に満ちている。
1年前、「CO2は減らすべきか?気候モデルには科学的な裏付けがあるのか?」といった記事が紹介された。
CO2を減らすべきか? 気候モデルには科学的な裏付けがあるのか?
気候変動のシミュレーションは、地球大気・海洋・陸地・氷塊などを数値的にモデル化するものである。気象の方程式をベースに、地球全体を3次元の格子に分割し、定期的に未来の状態を算出していく。モデルは物理法則に基づいているが、地球全体の100km以上のスケールに区切られており、都市や山脈、微細な雲などの場面は直接反映されない。そのため、これらの小スケール現象は「パラメータ化」と呼ばれる手法で近似する必要があり、これが予測の不確実性を生む一因となっている。
不確実性の4つの要因
初期条件の敏感性(カオス性):気候は非線形の複雑系であり、初期状態のわずかな違いが長期的には大きな影響を持つ。数十年後の気候結果は、大きく変わる可能性がある。
パラメータ化の限界:例えば、雲やエアロゾルが気候感度に大きな影響を及ぼすことが知られているが、観測や理論的解釈が十分ではないため、モデル内での位置づけが不完全である。
空間・時間分解能の制約:大型気候モデルは大気や海洋を100〜250kmの解像度で示すため、地域の気候や熱帯の対流の動態を正確に捉えられないことがある。これが地域的な気候予測の不確実性を引き起こす要因となる。
将来のシナリオ依存性:未来のCO2排出量や社会経済活動は予測が困難であり、これを元にした「不確定な未来」のシナリオが用いられる。RCP(Representative Concentration Pathways)やSSP(Shared Socioeconomic Pathways)と呼ばれる様々なシナリオが提案されているが、その選択が結果に大きな影響を及ぼす。
そして、このような情報の不確実性は、政策決定時に考慮されるべきである。気候変動の影響が実際にどれほど深刻か、またその根拠がどの程度信頼できるかは、これからの持続可能な社会にとって重要な課題である。特にRCP8.5やSSP5-8.5のような極端なシナリオが現実となる場合、気候がどのように変化していくのかを正確に把握することが求められる。温暖化の予測値は今後も変動するため、我々は柔軟なアプローチでこの問題に取り組む必要がある。
結論:気候モデルはどう向き合うべきか
気候モデルは、科学的思考を支える道具ではあるが、あくまでも立脚に過ぎない。未来の予測を行う上で、科学と政策の間には大きな距離が存在することを認識しなければならない。そのため、我々は正確な情報に基づく判断と持続可能な発展への努力を両立させていく必要がある。

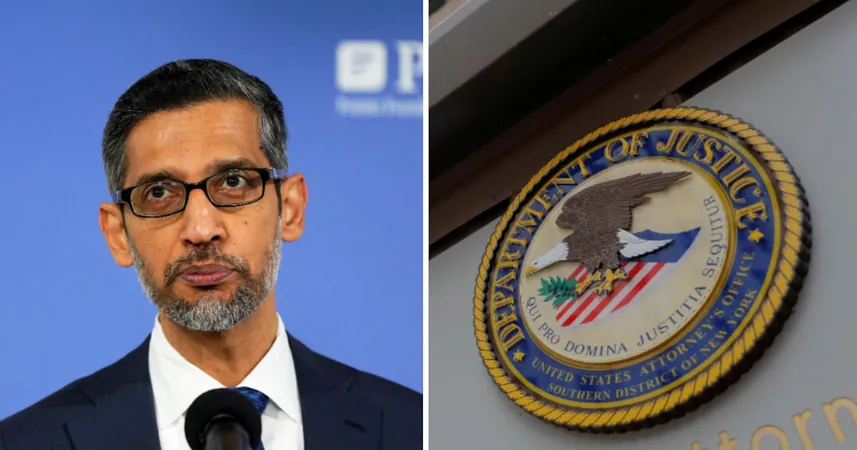

 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)