
「日本列島」に迫る「巨大断層」。それは「グラニット」の背後に隠されている?!
2025-04-03
著者: 陽斗
皆さん、4月5日(土)19:30!タモリさんが全国各地を訪れ、そこに隠された歴史や文化、地形の秘密を解き明かす街歩き番組『ブラタモリ』がレギュラー放送で再開します!【写真】日本には地震が多いのか…。地球科学で見える「列島の異変」と「次の大地震」の今回の記録は以前に『ブラタモリ』でも取り上げられた「霊岩(れいがん)断層」についてです!私たちが住む日本列島の構造とはいかなるものか?ブラタモリ—必見!! 地学46億年の歴史、地震のメカニズム、気候変動からの変化、日本列島の特異性、宇宙の成り立ちと進化……誰もが知っておくべき地学の教養。そのエッセンスが注目されているのが、「高校地学」だ。 本連載では、「最高の教養」である高校地学の中身を、わかりやすくご紹介する。地質学、古生物学、自然地理学、気象学、天文学、宇宙論など、幅広い学問分野の最新成果がめまぐるしく、存分に楽しみたいと思う。 本記事は、『まるで高校地学おもしろくて役に立つ、地学と宇宙の全常識』(嶋田博光/菅原善晴著)を一部抜粋・再編集したものです。
日本列島の構造とは
今回は、日本列島を地学の目で見ていきましょう。日本列島の地底の大部分(基盤岩)は、大陸プレートの先端で形成された追加体と、その一部が変成作用を受けてできた変成岩、マグマが冷え固まってできた火成岩などで構成されています。追加体とは、海嶺プレートが日本列島の下に沈み込む際に、海嶺プレート上の堆積物がほかれられて、大陸プレートの先端部に追加されたものです。
南西日本の地質構造
南西日本では、追加体を形成する地層や岩石が、東西方向に長く並列しています。代表的な追加体として、プレートに形成された秋吉群、ジワル群に形成された美濃・岐阜、白亜紀〜新第三紀に形成された四万十層などがあります(2-9-1)。追加体は、太平洋側の浜松で形成されますので、古い追加体は日本海側(大陸側)、新しい追加体は太平洋側(海側)に分布しています。追加体の一部は広域変成作用を受け、変成岩となっています。特に、広域変成岩は広い範囲に分布する場所を広域変成体と呼びます。南西日本には、高温低圧型変成岩(片麻岩など)が分布する帯状変成体や低温高圧型変成岩(結晶片岩など)が分布する三波層変成体などがあります。このように、追加体の成り立ちを探求することで、日本の地震活動の背景や今後の地震の予測に役立つ情報が得られるのです。



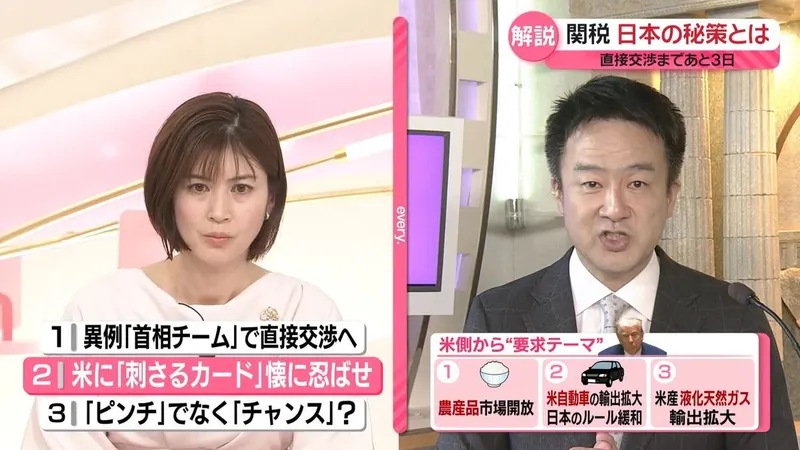

 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)