
日本人には独特の「共振性」がある!『地震のあとで』出演・井上剛が4度目の「震災の物語」で感じたこと(田幸和歌子)
2025-04-05
著者: 桜
1995年に発生した阪神・淡路大震災の後、村上春樹が手がけた短編小説『神の子どもたちはみな踊る』の中の4作を、震災から30年を迎える2025年の節目に連続ドラマ化した作品『地震のあとで』が4月5日から放送される。
『ドライブ・マイ・カー』原作の大江健三郎に通じると言われる物語においては、「人間社会を襲う猛烈な弾力とその影響」であり、原作と同じく「天災」「災厄」などを、現地ではなく遠い場所で受けた人間たちの喪失を描く作品でもある。
出演を手掛けたのは、ドラマ化・映画化された『その街のこども』(2010年~2011年)、朝ドラ『あまちゃん』(2013年度上半期)、映画『LIVE! LOVE! SING! 生きて愛して歌うことの劇場版』(2016年)など、震災をモチーフにした作品を数多く手掛けてきた井上剛さんである。
インタビュー後編となる本記事では、青春ドラマ的なミラクルを映像化するうえでの苦悩や、震災の物語を描き続ける理由について聞いた。
生身の人間で映像化するのが難しい文体
―原作となった村上春樹さんの短編はセリフが少なく、余白のある文学作品で、どう映像化するのか想像がつきませんでした。しかし、実際に拝見すると、あまりもの巧妙に再現されていて驚きました。その秘訣は何ですか?
井上:僕が小説を読んだとき、村上さんの文章は非常にノスタルジックであり、それだけが多く、余白のある文学作品だったのですが、映像として再現するのは難しい文体であることを実感しました。だからこそ、私は原作に忠実でありながらも、映像の中で生き生きとしたキャラクターやセリフを生き生きと再現する努力をしました。
ストーリーの形式、つまり、どこに難しさを感じましたか?
井上:セリフは大江健三郎さんが書いていますが、セリフの1行1行は原作から選ばれていたものが多いです。しかし、セリフに込めた意味が伝わるようにすることが、非常に難しい。生身の人間がやるうえで、あの作品を映像にするのは困難でした。
1200文字の形式を試みながらも、映像でその作品が持つ力を十分に発揮できているかどうか、自問自答を繰り返した経験があります。「御影駅で見かけたあの人、あるいはあの時代の作品」という感情は、私的なものとして扱われ、必然的に出た結論でもありました。
井上さんは自分自身の抱えている困難を素直に映像として残しながら、より多くの人が感情を共有できるような場を提供することを目指したと語っています。彼の取り組みが、多くの視聴者の心に共鳴する作品となることを期待しています。
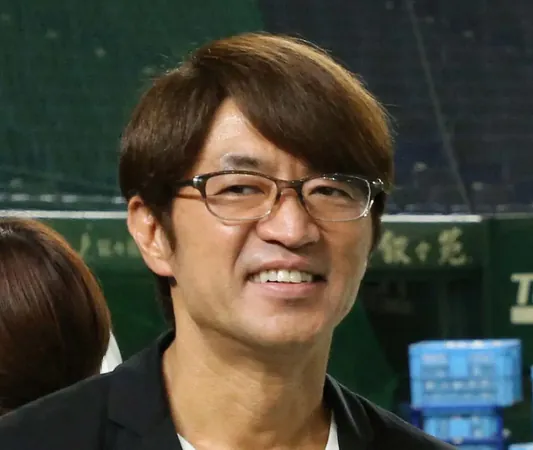


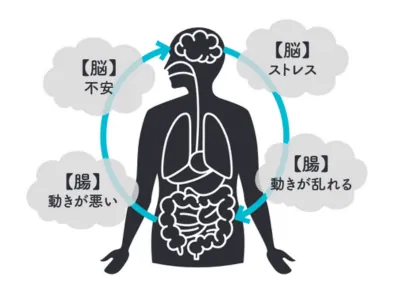
 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)