
榊原桃里には「どう書いても大丈夫という信託」がある。『御上先生』脚本家が語る想い(田幸 和歌子)
2025-03-20
著者: 愛子
冬ドラマにおいて数字・話題性・評価の総合点で「独り勝ち」とも言われる、榊原桃里主演のTBS日曜劇場『御上先生』がいよいよ最終回を迎える。東大卒のエリート文科省官僚の御上嵐が官僚制度に対する思いを描く作品であり、高校3年生の担任として教師に就く様子を描く異色作だ。
「この話題を掘り下げるのか」「攻めているな」という声がSNSには溢れているが、実は企画自体は2020年に立ち上がったものだ。月日を経て、TBSの看板・日曜劇場で放送されることとなった。
FRaU webでは、榊原さんへのインタビューを通じて、作品が生まれた背景について詳細に伝えており、後編となる本記事では、榊原さんがキャスティングに関するエピソードについて明かされています。
榊原桃里の演技に対する信託とその影響
—御上先生の人物像は、どのように作られたのですか。榊原さんの書きの部分もあるのではないか。
榊原:御上さんの名前は最初からあがっていましたが、あくまで書いてはいないんです。飯田さんから名前が出た時に、「榊原さんは『新時代作家』でも官僚をやっていて、しかも私の作品で、それでも受けてくれるなら榊原さんがいい」とおっしゃっていただきました。
榊原さんの場合、どう書いても「熱演」まではいかないという信託があって、思う存分書けていた気がします(笑)。最初はもってもされてる先輩を想定していたんですが、取材していく中で、優れた教師はみんな生徒たちに考えさせるということを知り、当初考えていた教師像からファシリテーターとしての優れた教師像に変えて、そこからは思わず書けました。
—「ダークヒーロー」と言われる登場人物に関して、まったくダークにならずすぐ生徒に信頼されるのかも面白いですね。
榊原:それは面白いところで、まず最初は「ダークヒーローにしたい」という思いがあって、登場させたのですが、描いているうちに「働くってこうだ」、あるいは「生徒にまかせる」みたいなことも考えに入ってきて、神秘的な存在のような面白さが登場したんです。最初は突き放して考えてたのに、心の距離感を大事にしないと伝わらないと時期に思いました。
冬ドラマに榊原桃里が注目を集めることの意味は、彼女自身の成長だけでなく、教育というテーマを通じて日本社会の変化を映し出す役割を果たしています。榊原さんのキャラクターがどのように受け入れられるかが大きな注目のポイントと言えるでしょう。

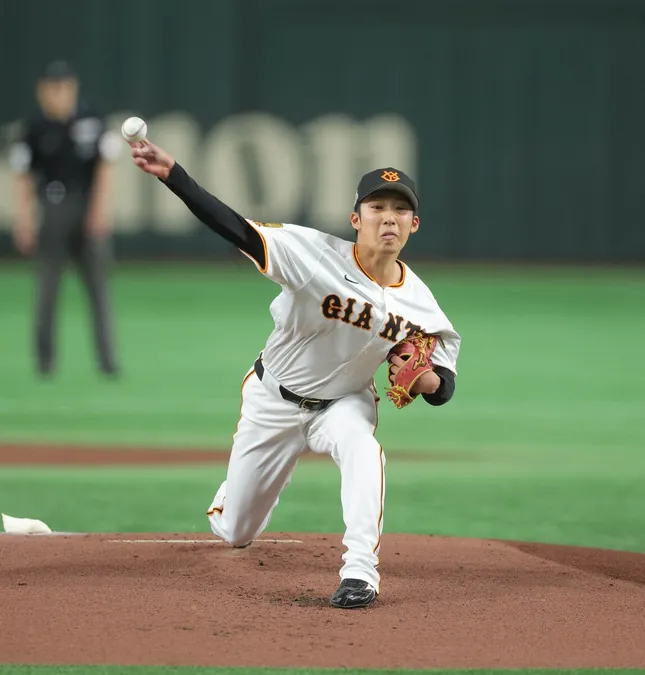

 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)