
身体的神経から作る「ボディオイド」で医療革命、だが倫理的論議も沸騰
2025-03-29
著者: 弘
現代の医療研究には深刻な問題がある。それは「人間の身体サンプルの不足」である。アメリカの科学者たちが、この問題を解決する可能性のある新しいアイデアを提案した。それが「ボディオイド」と呼ばれる技術である。
これは、衛生的にも倫理的にも扱いやすい人間の身体の代替物を作り出す技術だ。具体的には、実際の人間の身体を模倣する3Dプリンタで製造された血管や筋肉の構造を持つ生物素材でできている。
この技術は意識も思考もなく、痛みも感じられない。単純に肉体として存在するものである。この技術が実用化されることで、臓器を無制限に供給できる可能性があるが、それには倫理的な問題も付きまとう。
まるでSFのような話だが、この技術が実用化されれば、医学研究を大きく進める可能性がある。しかし、倫理的な問題も浮上する。
人間の身体が足りない、医療研究の重大な課題
成功したマウスの若返りにより、3Dプリンターで肝臓のプリントに成功した!こうした新たな医療技術のニュースは注目されているが、一方でこれらの技術がもたらす倫理的な問題についてはあまり語られていない。
疾病の中には、他の人から臓器を取り入れて移植することができる場合もあるが、日本では臓器移植ネットワークによると、そうした患者が臓器移植を受けるまでには数年もかかる。これらの技術が普及するためには、一体どれだけの時間がかかるのでしょうか?と疑問が残る。
スタンフォード大学のポスドク研究員カーステン・T・チャールズ氏によると、こうした問題はたった1つの根本的な問題に起因している。
それは医学・創薬の研究や臓器移植に使える身体が圧倒的に不足していることである。
新しい薬の研究に使える身体がないから、生活的に人間と同じような動物モデルが利用される。しかし、これからは技術の進展に伴い、人間に近い「多能性動物」を利用して、研究が進むはずだ。
例えば、従来型の肉体を「ボディオイド」に変えることで、医師や創薬の研究に利用できる身体が急増する可能性がある。
この「ボディオイド」技術は、稀少な病状の治療などに役立つとされている。
もしこの技術が実用化される過程で、その動物がどのような進化を遂げるのか、またどういった倫理基準が必要になるのかを考えながら進めていくことが大切です。大学などでは、この技術の進展がもたらす可能性についての議論が活発化しています。
その一方で、衆目を集める技術が実際に利用されるようになるには、倫理的議論や研究者間の合意が重要です。義務感から取り扱われることなく、進んで利益が生まれることが求められます。
全ての知識が結び付き、この技術を推し進めることが求められているのです。私たちはこの技術がもたらす未来に、希望を持たずにはいられません。
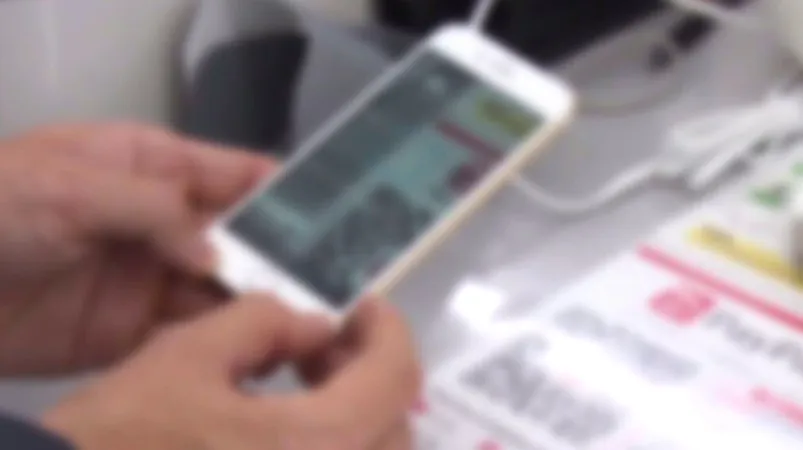

 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)