
世界中の生物がデータを集める「動物のインターネット」 環境問題にも資金集めさえますね!
2025-04-04
著者: 裕美
世界中の生物がデータを集める「動物のインターネット」
動物にさえも記録計を装着し、行動履歴や周囲の環境に関するデータを集める「バイオロギング」を使った研究が盛行している。動物の生態を知るために重要だったが、世界中で集められているデータを統合して、海洋の現状を知ろうという概念が誕生。
「モノのインターネット(IoT)」にならい、「動物のインターネット(IoA)」と呼ばれ、温暖化や海洋汚染といった環境問題の解決に貢献できる可能性も見えてきた。
日本発信の学術用語
クラゲやウミガメ、海鴨といった動物は広域に移動するため、直接の観察をし続けることが難しい。こうした動物に温度計や加速度計、カメラといった記録計を取り付けることで、動物の生態に迫るのがバイオロギングです。手法としては1950〜60年代にはあったとされるが、バイオ(生物)とログ(記録を取る)を組み合わせた学術用語が誕生したのは2003年のこと。第1回国際バイオロギングシンポジウムが東京で開催されたタイミングに提案された、日本発信の言葉です。
水温や位置情報、物体の速度が変化する様子を示す加速度のデータが集められる。人間が行くのが難しい場所での動物の行動や周囲の状況を調べることもできる。技術の発展に伴い、トンボやハチのような小さな生物に取り付けられるようになったという。
動物を理解するだけでなく、海洋環境を観測する手法としても、重要性が増している。
たとえ波間に埋もれた海は船で探索することが難しいが、そうした場所で漂うアザラシに装着した記録計で、海洋環境データを集める研究が行われている。
漂流して水中データ取得
神戸大学の坊田高志助教(動物生態学)らは、調査船や人手による観測を行った結果、魚の動きや周囲のデータを集める手法について前月発表した。坊田助教は「水温変動や濁度、様々な生物多様性の保全といった海の問題の解決に寄与できる」と強調する。
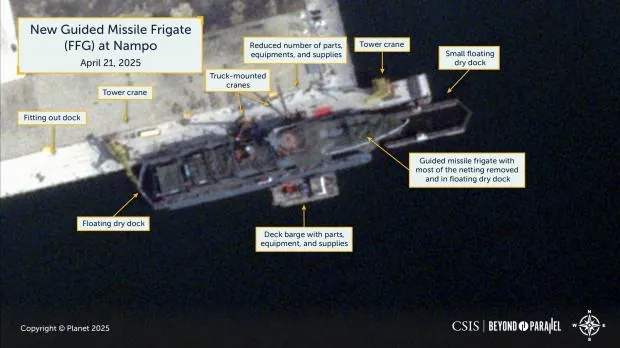

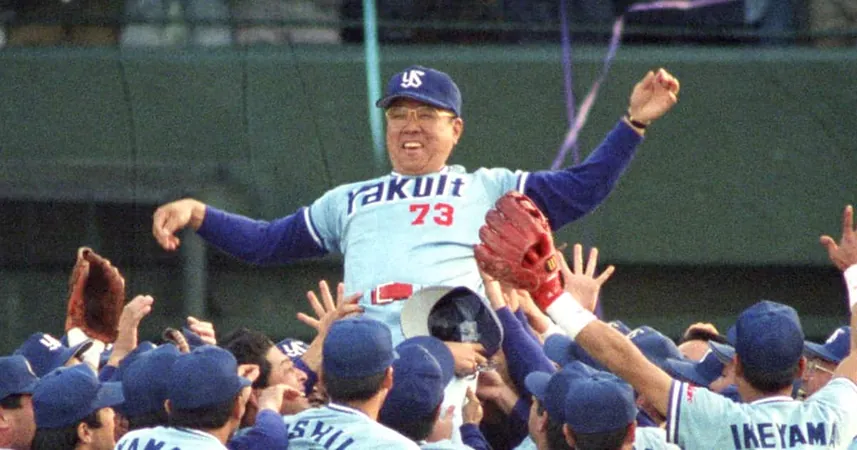
 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)