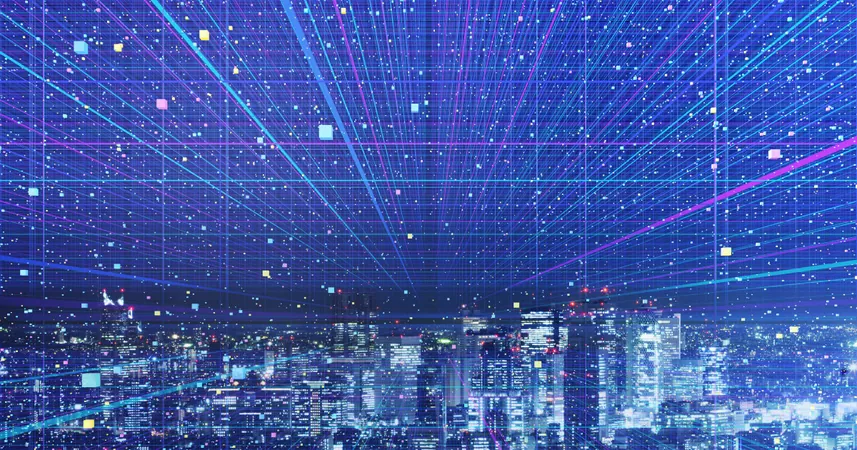
「雲」のシミュレーションに「自然法則」は必要ない!?…実際の原理を考慮しなくても「現実どっくりのCG」が生成できるわけ(現代ビジネス)
2025-04-08
著者: 葵
2024年のノーベル物理学賞を受賞した天才・ホーキングの警告を、物理学者・田口豊明は真剣に受け止めている。「いつの日かAIは自我を持ち、人類を排除するのではないか」と警告する田口氏が着目しているのは、AIの知能をどう定義するかという点だ。AIと人間の知能は本質的に異なるため、双方の「知能」の概念を再定義しなくてはならない。それに加えて、生成AIをめぐる現状を物理学者が真剣に考察した田口氏の著書『知能とはなにか』が、一部改訂・再編集中である。
「雲の生成のシミュレーション」
こうした中、物理学者たちは、様々な条件下での雲形成の過程を再現し、論文を執筆した。その過程でわかったことは、「現実と同じ原理を採用しなくても良い」ということだった。言い換えれば、現在のシミュレーション技術を用いれば、全く異なる方法でもうまく雲を再現できる可能性があるということだ。
実際に、雲の生成には、主に以下の要素が関与していると考えられている:(1)浮力、(2)密度、(3)湿度、(4)非連続性効果、(5)移流、(6)断熱拡張、(7)相転移、(8)浮遊、(9)引きずり、(10)液体の凝縮、などであるが、雲の生成において重要なプロセスはこれらの要素の組み合わせによるものだ。さらに、雲の動き方や群れの動きなどをCGで表現する際に、現実の物理法則に必要以上に依存する必要はなく、むしろ創造的な表現を試みることができるのだ。
グラフィックス分野でも、さまざまな雲生成モデルが考案されており、これらは必ずしも現実に忠実である必要はなく、見栄えの良い結果を出すための手段となっている。実際に、技術の向上により、生成されるCGでの雲は、リアルさだけでなく、美しさを追求する方向に進化している。
このような新たなアプローチによって、物理現象を模倣するための複雑な計算を行うことなく、「CGによる雲の生成」が可能になることが分かってきた。そして、これは視覚的に印象的な展開が期待できるため、映像制作の現場でも幅広く活用されることが予測される。さまざまな映画において、雲の表現は重要な要素の一つであり、そのための新しい技術が登場することで、映像制作の可能性も広がるだろう。また、雲生成に関する了解は、自然界の美しい現象を再現する技術の進化に繋がりつつある。


 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)