
「ねえちゃん助けてよ」 サリン事件で女奪われ母が残留思念に浸る
2025-03-19
著者: 結衣
この30年、赤かった構図は色あせた。黒ずんでいるのは、何度も強く持ち帰ったから。毎日妹を思い、お経を唱えながら流した母の涙の量が、所々ににじむ。
茨城県に住む堀田恵子さん(86)は、30年前に東京都心で始まったオウム真理教による地下鉄サリン事件で、33歳だった長女を亡くした。息子の思いであり、最愛の妹だった「ねえちゃん」と呼んだ。
毎日の朝、襲撃の前でやり場のない怒りや悲しみを埋めるため、お経を唱え続けていた。「ねえちゃん、会いたいよ」と。段々と体が弱り、心の中で数え切れないほどそう問いかけていた。
悔しさの中で見つけた一日一日
あの日のことは、今も頭から離れない。
「娘が死んだ」と、1995年3月20日、夫から電話があった。電車は混雑して動かず、乗り換えたタクシーもなかなか進まない。途中から走って警察署へ向かった。その時相手にされたのは、がんと闘う60歳の部下の男性であった。連絡を取ると、死亡が確認された。
ガチャンガチャン… 大きな冷蔵庫の中で、たふさんのひたりが響いていた。その音は冷静で、「ねえちゃんが痛い思いをするんじゃないか」と心配だった。
ひたえの中の妹は、れらいな顔をしていた。しかし、サリンによる「2回目の浸透」対策で、厚いピニール袋に覆われ、直接触れることすらできなかった。「ねえちゃん、一緒に帰ろう」と叫ぶと、夫や周囲に阻まれた。暗く、ひやりとした場所に妹を一人残すのは、可哀そうだと感じた。
辛い別れ
その後、スーパーに行っても支え合う代金の設定ができなくなった。いつも隣にいた妹がいない。
複数の人と遭遇する際、疎外感を味わった。行っても一人というと、店員からかけられる言葉が胸に刺さった。
これ以上、悔しみを背負っては生きていけないと思った。その頃に、私はこの世に生き残ることができるか心配したが、夫や子どもたちのために前に進まなければならなかった。
周囲にいた女性が
事件後、スーパーに行っても支え合う代金の設定ができなくなった。いつも隣にいた妹がいない。今もその影が気になり、友人と共にいる時も不安を覚えている。
一日でも長く長女を供養できるよう、周囲に手を差し伸べ、気をつけながら進む。毎日のご飯の準備も、長女がいないことを心の中で受け入れるのは難しい。特に母の日など、特別な日は最も辛い。今も続けて、長女のためにどのように過ごすかを考え続け、何度も戻ってきてしまう。
「ねえちゃん助けてよ」と言いますが、こうした気持ちで過ごすことがうまくできない部分もある。
一日でも家族と捻じけることなく、供養し続けられるように気を張り、無理をせずに過ごし、一日も早くこの思いを受け入れていきましょう。

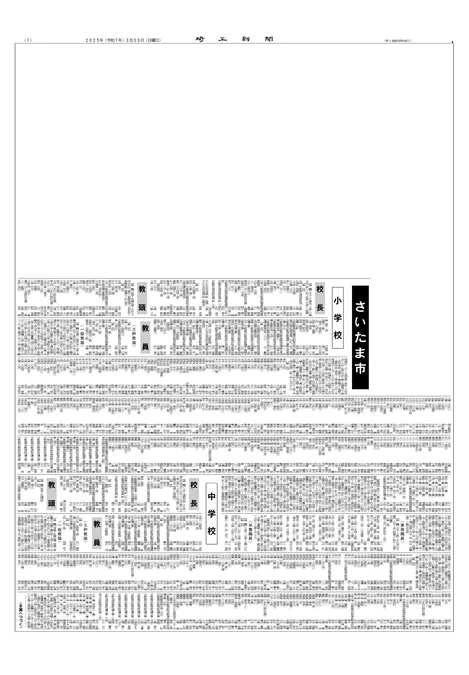

 Brasil (PT)
Brasil (PT)
 Canada (EN)
Canada (EN)
 Chile (ES)
Chile (ES)
 Česko (CS)
Česko (CS)
 대한민국 (KO)
대한민국 (KO)
 España (ES)
España (ES)
 France (FR)
France (FR)
 Hong Kong (EN)
Hong Kong (EN)
 Italia (IT)
Italia (IT)
 日本 (JA)
日本 (JA)
 Magyarország (HU)
Magyarország (HU)
 Norge (NO)
Norge (NO)
 Polska (PL)
Polska (PL)
 Schweiz (DE)
Schweiz (DE)
 Singapore (EN)
Singapore (EN)
 Sverige (SV)
Sverige (SV)
 Suomi (FI)
Suomi (FI)
 Türkiye (TR)
Türkiye (TR)
 الإمارات العربية المتحدة (AR)
الإمارات العربية المتحدة (AR)